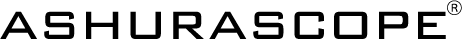いつから可能になった技術なのか
言葉の定義からいえば、投影してスクリーンと関係があればいいのでOHPでも影絵でもできますから昔から同じようなことはあったと思います。
映像と現実とのシンクロ、2つを合わせて1つのコンテンツに見せるという手法でいえば、アニメーションの発明とほぼ同時に行われ始めています。
1914年「恐竜ガーティー 」と言う作品ではアニメーションの恐竜をスクリーン登場させその前に実際の演者があらわれ、その恐竜とやり取りをするといったパフォーマンスがありました。お辞儀をさせたり、餌をやったり最後には演者がスクリーンの中に入ってしまい、彼もアニメーションとなって恐竜と去っていきます。
驚くべきことに現在プロジェクションを使ったパフォーマンスと同様のことは既に行われていたのです。
簡単に説明すれば、映像だけで完結させない表現として考え出された、いわゆる「コロンブスの卵」的発想ですから個人で制作していた人は昔からいた思います(当社の代表は1994年頃から制作していました)。 それが現在注目されるようになったのにはプロジェクション技術の発展があります。非常に高解像度で高輝度のプロジェクター開発されたために、巨大な建築物にも映像を投影できたり、実物と間違えてしまうほどの画質を投影できるようになりました。また映像の補正技術も進化して、複雑な形状の補正が可能になりプロジェクションマッピングを制作することの技術的ハードルが下がったためだと考えられます。
▲ 『恐竜ガーティ』ウィンザー・マッケイ